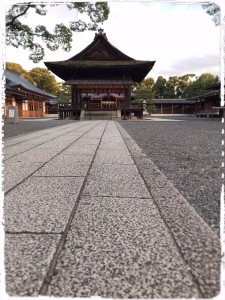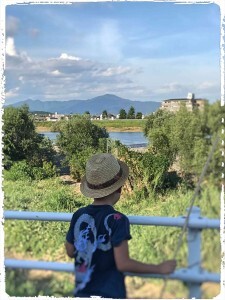大瀧詠一さんと子猫
大瀧詠一さんを初めて認識したのは学生の時だったか
毎年年始に山下達郎さんと対談していたラジオで、
まじめな口調でふざけたことをいう、よく分からないオッチャンだなあという印象でした。
その後、分母分子論や普動説等、深い洞察を知り、
もちろん、日本のポップス先駆けでいることによる他の人々と同様
経済的な恩恵、いわゆる飯が食えるということもあったにせよ、
実に自らの理論と行動の一貫性をぶらさずに、
自らの持ち分を成熟させ続けた方でした。
(「風をあつめて」。紹介するのを「五月雨」と悩みましたが時期的にこちらにしました)
先月、台風の前の日に
我が家に子猫が迷い込んできて、
どんなに待ってもお母さんが来ず、
うちで引き取ることにしたのです。
様々な生き物と暮らしてきたけど、
猫は初めてで、
その生きることと自らの持ち分に真っ直ぐな様子をみて、
大瀧詠一さんを思い出して
彼にまつわる曲をかけながら、
離乳時期なので手ずからご飯をあげたり、
まだトイレが自分でできないので出させてあげたりと、
現実的な作業をするところも
実に大瀧さん的だなあと勝手に思うのでした。
以上、我が家に子猫がやってきた話でした。